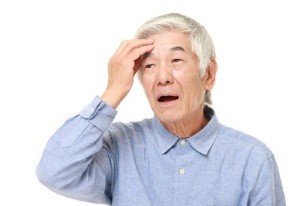成人が歯をうしなう原因の第一は歯周病です。
日本では、40歳以上の人の80%以上の人が歯周病になっているといわれています。
症状は人それぞれなので、ごく軽い人から、重症の人までさまざまですが、決して自分と無関係な病気ではありません。
歯周病とは、歯を支えている組織を知らないうちにむしばんでいる病気ですが、多くの人は、かなり病状が進行しないと、自覚症状があらわれません。このことから、歯周病の治療は手遅れになりがちです。
また、歯周病は単にお口の中だけの問題ではありません。
歯周病菌が、血管から全身を駆けめぐり、これによって狭心症や心筋梗塞になるリスクが健康な人よりあがり、流産や早産のリスクも高まるといわれています。
このように歯周病は、全身の健康に影響をおよぼす生活習慣病だといわれています。